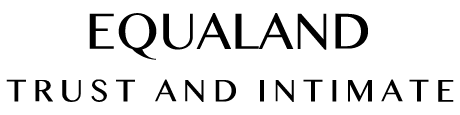ものづくりの背景に敬意を払いクリエーションを讃える。サステナブルをテーマに、アーティストや起業家をはじめ想いを共有する挑戦者たちを紹介。彼らのヴィジョンから自分らしいスタイルのヒントを見つけ出します。
法律家の水野祐さんと考える、日常の解像度を上げるルールの楽しみ方
7月2日から東京・六本木の21_21 DESIGN SIGHTで「ルール?展」が開催されている。日常のあらゆる場面で私たちの行動を形づくる「ルール」。様々なタイプのルールを題材に、新しいルールの“見方・つくり方・使い方”を考える展示をめぐる中で見えてくるものとは何なのか?ディレクターを務める法律家の水野祐さんに、展示を通して伝えたい思いを聞いた。

ルールはときに柔軟でゆらぎをもつもの
ー法律家として、様々なアプローチで“ルール”のイメージを変えようという発信をされてきたことが、今回の「ルール?展」で展覧会ディレクターを務めることとなったきっかけになっているのではないかと思います。水野さんが著書でも記されているよう、「法律やルールの中に、様々な分野のイノベーションを促進する存在として、ポジティブな可能性を秘めている」という考えに至った経緯を教えてください。
学生時代に音楽や映画など、いわゆるサブカルチャーに傾倒していたこともあり、弁護士になったばかりの頃は自分が恩恵を受けてきたような作品を生み出すクリエイター達がより表現を追求できるよう、法的な側面からサポートしたいという思いでいました。そんななかで、僕が弁護士になった約10年前は、GoogleやUber、Airbnbなどといったや法のグレーゾーンを巧みに使いつつ新たなサービスを提供する米国企業が注目されるようになる一方で、自分自身も法律家という立場から思考停止とでもいうべき日本特有の法令遵守主義の流れを変えていきたいと思うようになりました。
弁護士というとトラブルが起きた時に解決する役目というイメージがあると思いますが、それだけでなく、新しいビジネスや表現がより円滑に、豊かになる土壌を作るための地ならしをすることも仕事の一つですし、企業やクリエイターと一緒にグレーゾーンを探り、古くなっているルールを疑い、新しいルールを提案していけるのではないか、という気持ちは一貫していると思います。
ー今までは執筆や講演等を中心に発信されてらっしゃいましたが、「ルール?展」のディレクターとして、伝えたいことを展示という形式に落とし込むのには、どのような面白さ、また難しさがありましたか?
僕自身、展覧会にディレクターとして参加するのは初めてのことでしたが、共にディレクターを務めるコグニティブ・デザイナーの菅 俊一さんとキュレーターの田中みゆきさんの2人が経験も実績も豊富なので、とても頼りにしていました。菅さんはテーマや課題をどうすれば分かりやすく伝えることができるのかをシャープに分析して解決法を見出す、いわばコミュニケーションデザインのプロ。それに対してみゆきさんは彼女がやってきた障害のある方とのコラボレーションなどに顕著なマイノリティに対する目線はもちろん、言葉にしづらい、あるいはまだ言葉にできない問題や領域をアート的な想像力で提案し、鑑賞者にいいモヤモヤ感を与えるような展示をキュレートしたり、自ら作品制作することで展覧会の企画を引っ張ってくれました。とにかく、あらゆる過程においてサボらない2人なので、会場である「21_21 DESIGN SIGHT」や「東京ミッドタウン」自体のルールの成り立ち、意図を学ぶことにはじまり、グラフィックのルール、会場構成、オンラインのルールも自分たちでつくりました。
今の時代、ルールというと、どうしてもリテラシーなどの問題に直結し、意識が高い人に向けた展示になってしまうのではないかという懸念があったのですが、ディレクターチーム全員、それは避けたいという思いが一致していたので、方向性を決めるのは話が早かったです。展示に対し鑑賞者が積極的にアクションを起こすような体験を通して、ルールを一緒に考えたり、作っていく楽しさを感じられるようなものにしたいと力を注いだつもりですが、まだ始まったばかりで成功しているかどうか判断できず…。ただ思ったより若い人がたくさん来てくれているようなので、間口の広さに関しては成功したかなと思っています(笑)。
ーいわゆるアートやデザインの文脈ではない作品も含めて展示作を選ばれたと伺っています。それはどうしてなのでしょうか?
田中功起さんの「ひとりの髪を9人の美容師が切る(二度目の試み)」をはじめ、既にある作品をキュレーションしたものもあれば、展覧会のコンセプトとルールを伝えて新作としてつくってもらったものもあったり、いい意味で展示作品の振り幅は広いのではないかと思います。できるだけデザインやアートの文脈にはないクリエイター、作品も選んだ理由というのは、やはりルールというものを多角的に扱いたかったから。法律だけでなく、自然法則とか慣習、暗黙知や道徳、倫理などさまざまなルールを見せるためには必要なことでしたし、またどうしても説明的なパネル展示が多くなりがちなところを、そうではない形でどうルールを体験してもらうか、というところはディレクター3人で工夫したところです。
ルールや法律、契約といった決まりごとは自由を阻害するもので、煩わしいものと考える人が多いのではないかと思うのですが、ルールが存在するからこそ、破るという選択肢も生まれるし、制約があるからアイデアも湧くもの。実際、ここ数年の様々な企業のアクションからも見て取れるよう、ルールを単に“縛るもの”としてとらえるのではなく、よりよい社会を作っていくためのツールとして更新していくべき時期が来たと感じています。


今の世の中の流れや本展覧会のテーマでいうと、ルールの共創というのがあるのですが、これは言うのは簡単だけど、実現するにはたくさんのハードルがあるし、本当にそれでよいルールができるのか、という疑問もある。まさに共同作業の欺瞞を伝えたいと思い、選定している作品もあるのですが、ディレクターチームのなかではそういう課題についてもきちんと逃げずに取り上げようという意思がありました。残念ながら、ルール作りに参加している感覚が持ちづらいのが現在の日本ですが、本展でさまざまなルールに触れることで、ルールの面白さ、ゆらぎ、柔軟性といった一面にも触れて、そもそも自分にとってルールって何?と身の回りのことから考えてみて欲しいと思っています。
ルールがあるから余白が生きる
ー実際に展示がスタートしてからも、ルールが追加されるなど、日々更新されています。始まってみて気づかれたことはありますか?
最初からあえて余白を残しておいて、起きたことに対して必要であればルールを作っていこうというのがコンセプトの一つなので、実際に会場を見て回ったり、SNSに「#ルール展」で投稿されるものをチェックして、会場に設置したルールや余白がどのように活用されているのかをぜひ見てもらいたいです。作品ではないのですが、展示の一つに、ある一定のルールさえ守れば、会場内で自由に使用することができる「箱たち」があるのですが、このあいだ突然のスコールがあった際、多くの来場者の方が中庭に向かって椅子を並べて、激しく降り注ぐ雨を鑑賞する、ということが起きました。椅子が自由に動かせることによって、雨という自然現象をじっくり鑑賞できる新たな展示が増えたかのようで、とても嬉しかったですね。もちろん現時点ではうまく機能していないものも一部あって、どうしたら来場者が参加してくれるか、オープンした今でもディレクターチームで打ち合わせを重ねています。ルールというのは、メンテナンスされながら運用されていくべきだということにわたしたち自身も日々気付かされますね(苦笑)。

その時にたまたま居合わせた人の行動だったり、混み具合だったり、天候などが作用して、展示会場の余白に日々変化をもたらしているのが見所の一つ。空いている平日にはゆっくり展示を観に来ていただいて、混み合う土日は来場者の行動を見て自分の内面にどのような変化が生まれるか、感じてもらうのも面白いと思います。目まぐるしく変化する社会情勢のなかで、ビジネスでも、日常の生活でも、既存のルールを疑ったり、距離をとったり、新しく作り直したり、というようにルールに対するものさしや、ルールメイキング思考が求められているように思います。この展示を通して、そうした思考に触れることができるはずです。
ー最後に、水野さんが法律家として、また一個人として自身が日常的に自分に課しているルールはありますか?
マイルールみたいなものはあんまり思いつかないのですが…、法律家・弁護士としては、既存の法分野の知識をアップデートすることは当然のこととして、それ以外でも新規の、少し意外性のある分野であっても、声をかけてもらった時にいつでも打席に立てるように自由研究を重ねています。特に誰にも話さず自分が興味のあることを、本を読んだり、シンポジウムに参加したりして、掘り下げているのですが、言動の端々に出るものなのか、まさにちょうど自分が自由研究していた分野のお仕事のご依頼をいただくことも不思議と多いように思います。

一個人としては本当になくて、朝8時に起きる、くらいですかね…。あとは値の張る本は率先して買うようにしています。高い本はなかなか売れないものだからこそ読んでいる人も少なく、人とかぶらない情報が手に入ると思っているので。あと同じく、老後にとっておきたいレコードを一つひとつ買い集めてはいますが、最近の整備されたネットショップだと欲しいものが見つかりやす過ぎて、もはや“老後に〜”という大前提のルールは破綻していますね。広い家に住みたいという願望もなければ、高級車も別に要らないし、服や靴ならもう十分にある。そんな言い訳を見つけては、僕の人生史上いま最大にレコードに投資していますね。つまるところ、一個人としてはルールを守るのが苦手な人間ってことになるかと思います(笑)。
水野 祐
法律家。弁護士(シティライツ法律事務所)。九州大学グローバルイノベーションセンター(GIC)客員教授。Creative Commons Japan理事。Arts and Law理事。慶應義塾大学SFC非常勤講師。note株式会社などの社外役員。著作に『法のデザイン −創造性とイノベーションは法によって加速する』、共著に『オープンデザイン参加と共創から生まれる「つくりかたの未来」』など。
Twitter :@Tasuku Mizuno
■ルール?展
会期:2021年7月2日(金)〜11月28日(日)
会場:21_21 DESIGN SIGHT ギャラリー1&2
開館時間:平日11:00〜17:00/土日祝11:00〜18:00(入場は閉館の30分前まで)
休館日:火曜日(11月23日は開館)
入館料:一般1200円、大学生800円、高校生500円、中学生以下無料
主催:21_21 DESIGN SIGHT、公益財団法人 三宅一生デザイン文化財団