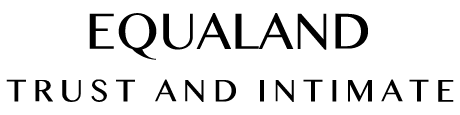ものづくりの背景に敬意を払いクリエーションを讃える。サステナブルをテーマに、アーティストや起業家をはじめ想いを共有する挑戦者たちを紹介。彼らのヴィジョンから自分らしいスタイルのヒントを見つけ出します。
“素材オタク” 坂田英一郎が歩む 天然の上質な機能素材への終わりなき旅
晴れが続いた東京の1月、ぽっかりとその日だけ恵みの雨が降り注いだ。
音もない霧雨の代々木公園に現れたのは、あらゆる素材を司る坂田英一郎だ。EQUALANDのもの作りの基盤は、坂田が積み上げてきたすべてにかかっていると言っていい。乾燥機にまでかけられるカシミア、薬剤を一切使わない自然素材による草木染め。普通だったら耳を疑うようなその手法を、坂田は知っている。これらの実現がどれだけ稀有であるか、いかに偉業であるか。40年以上注いできたものづくりを通して彼が守ってきたもの、そしてEQUALANDに込めた思いを聞いた。
坂田英一郎がファッション業界に入ったきっかけはジーンズだった。デザイン学校に行かずしてジーンズ作りを極めるため、時間を惜しんで工場の2階に住み込んだ。昼はデザインや企画を考案し、終業後は工場に戻って縫製や裁断を学ぶ日々。より穿きやすくて上質なデニムを求めて研究に勤しんだ。研究は徐々にデザインに始まり生地から糸、生産背景の“川上”にのぼっていく。

素材を突き詰めて出会った発見が人生を変えた
「僕にとって理想的なのは1940年代のリーバイスでした。穿いていくと縦と横の糸が緩んで柔らかくなって、洗うとキュッと締まる。これと同じ品質のものを作るために自分の持っているデニムを解体して、糸の撚りから何から全てを研究しました。しかし見た目は一緒でも同じようにならない。ついに原点に立ち返って当時の糸作りの背景を考えたんです。果たしてこの頃の畑では農薬が使われていなかったんじゃないかと」
1980年代後半のバブル全盛期。ミシシッピにある農園の土壌は、すっかり様変わりしていた。大量生産に合わせて農薬をばら撒き、良質なコットンの基盤となる乾いた土壌の代わりに水分量の多い土地での生産。しかし、アメリカのオーガニックコットン農家に出会った坂田は、昆虫学者サリー・フォックスさん監修のもとに天然の防虫剤を開発し、生産を促した。当時紹介したメーカーたちは30年を経った現在でも直接のやり取りをしている。オーガニックのコットンの生産に成功し、理想の生地づくりは結果的に大成功を収めた。さらに、課題である本藍染を叶えるために、沖縄へ飛ぶ。
日本の藍染めは全て合成染料に変わってしまっていて、本藍技術が残っているのは硬水と軟水がどちらも流れる沖縄だけ。しかし、飛んでいって頼み込んで染めてもらえるほど甘い世界ではない。それから数ヶ月、坂田が結んだ新たな絆が美しい本藍という文化の継承へつながり、沖縄での本藍の成功をきっかけに、草木染めの可能性を広げることになった。

自然素材に徹底した草木染めが完結へ
草木染めは植物由来の生地に染まりにくく、薬品で抑えないと色が落ちる。その難点を解決して以来20年以上、今は人間が作ることのできる3800色を全て草木で染めることができる。原料には、千葉や埼玉の農協やお茶の伊藤園など廃棄処分になるものを使って染色の研究を重ねた。現在、EQUALANDの草木染めの原料になっているのは、「SUNSHINE JUICE」の搾りかす。アメリカから日本で初めてコールドプレスジュースを持ち込んだコウノリ氏は、坂田のサーフィン仲間だ。荒波に立ち向かうもの同士、自然由来のサーキュラーエコノミーを守り続けてきた。

漂着するプラスチックゴミと地球環境へのアクション
海に浮かび、浜に打ち上げられる様々な言語のプラスチック容器。鯨の体内に詰まった海洋ゴミのニュース。サーフィンを通じて地球環境の変化を目の当たりにした坂田は、千葉の勝浦で20年以上毎週、ビーチクリーン活動を続けている。
「海の水分は雲になり、山から雨を降らす。雨が木々を育てて木々は酸素を出し、山に染み込んだ水が鉱石などを通して綺麗な水となって生き物を潤す。草花が咲いて実ると昆虫や動物の命が育まれていく。人間の体は70%が水。水の大切さを考えると海が大切ということがわかるはずです。海を汚すことに対して、微力であってもできることをやり続けています。
ペットボトルやプラスチックが世界でリサイクルできているのは全体の15%で、残りは捨てられるか焼却で不純物を出しているんです。でも、アルミ缶は溶かして作ってもう一度作ることができる。だから僕は、コーヒーはペットボトルではなく缶コーヒーを買うようにしています。一人の力は知れているけれど、とにかくやってます」

天然の動植物がもたらす効能と自然の機能素材
大量生産を促し便利さを追求した結果、変容した食生活は心身に影響を与え、化学薬品漬けの下着を纏って皮膚病を患うこともある現代。自然素材をもう一度見直してほしいと、坂田は訴える。
「例えばウールは、夏は熱から守り、冬は寒さから体温を守ってくれる天然の機能素材。毛はキューティクルのウロコ状のところに水が溜まるので自然の撥水力を持っているので、吸水速乾、撥水、UV遮断(熱を入れない・出さない)など8つの機能があらかじめ備わっているんです」
さらにデニムを追求するときに身についた、植物の効能。本藍には虫や爬虫類の忌避効果があるため作業服として重宝されていた。草木の効能は草木染めにも発揮されている。さらに現在、江戸時代から難燃の壁塗料として使われていた鉱石を研究し、来季に向けて湿度調節機能を持つ天然素材の開発を最終調整している。
ふくよかな土壌で育った植物、ありのままの自然で伸びやかに暮らす動物たち。微生物や鉱物を始めとした、目に見えない有機物がうごめく豊かな環境から収穫された自然素材の服は、自然環境に適応するに十分な機能をしっかりと携え、着るほどに肌なじみが良くなり、驚くほど長持ちする。所有する服の数が増え服を知るほどに、良質なものが一定数あれば十分に豊かで満足を実感するという。坂田が人生をかけたものづくりは、着る人の人生を見据えた質の高さを持つ。

余剰在庫に命を。職人たちに名誉を
ネイティブアメリカンは、目の前にどれだけ獲物がいたとしても家族が足りる分だけしか狩ることはないという。命をいただけば骨や毛皮を一切捨てずムダを残さない。先住民の知恵から真逆の立場をとる大量生産。特に、工場の余剰在庫は、坂田にとって悩みの種であった。
EQUALANDの製品の中には、大手の高級ブランドがキャンセルした糸や生地を縫製工場や生地屋から譲り受けたものがある。それらを安価で買い取り、3倍の工賃で取引するという仕組みを立ち上げた。
「煌びやかなブランドを実際作っているのは工場の職人たち。しかしながら小売店(川下)ばかりが儲かるシステムになっている上、大きなブランドは自分らが発注したものを簡単にキャンセルするんです。それを見て何かできないかと」

EQUALANDのアイテムについた信用タグには、農家から糸、生地、縫製といった生産ラインのすべての担当者の名前が記されている。すべての人に平等に、と願いを込めて名付けたブランド名の通り、産地から工場で働く一人の労働環境にまで目を光らせて丁寧にものづくりを行っている。トレーサビリティが求められる現代になってやっと自分がやりたかったことが形になってきたと坂田。
「大量に作って、着なくなって売れなければ捨てるのが当たり前の今。消費から出るゴミを止めるためにはと考えました。今僕がやっているのは、いい素材で着心地が良くて、大切に長く着てもらえるものをできる限り安く作ること。5年、10年と着られる服のコストについて考えてもらえたらと。
今の若い世代の間には、家族との心地よい時間を大切にしたり、社会貢献を理由にものを買う人々が増えています。環境問題にも目を向けている今だからこそ、天然のもので公害を出さない良い衣類の価値がわかってもらえると思っています」

Photographer_ Syuya Aoki
Interview_ Yuka Sone Sato
Editorial Direction_ Little Lights