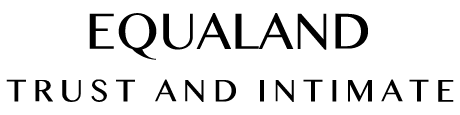ものづくりの背景に敬意を払いクリエーションを讃える。サステナブルをテーマに、アーティストや起業家をはじめ想いを共有する挑戦者たちを紹介。彼らのヴィジョンから自分らしいスタイルのヒントを見つけ出します。
日常のありのままの物語をすくう、イトウナツミの美学
EQUALAND TRUST & INTIMATEのヴィジュアルを手がけたアートディレクター兼フォトグラファーのイトウナツミさん。グラフィックデザイナー業の傍らほぼ独学でフォトグラフィーを学び、現在はファッションやライフスタイルに関わるデザイン業をこなしながら、自らの作品も意欲的に発表している。旅が好きで、旅先で出会った気になったものは無邪気に持ち帰る。それが石や流木であっても、持ち運ぶのに困難な大きな花瓶であったとしても。そうやって彼女は、広大な世界のかけらを少しづつ集めながら自分の世界を形成してきたのかもしれない。一貫した美学をたたえる作風に秘められたイトウナツミの世界を紐解いてみたい。
撮影は、広島県の尾道市を代表する複合施設、尾道LOGを中心に行われた。インドの建築チーム、スタジオ・ムンバイが日本で初めて手がけた建築物であり、かつての集合住宅をリノベーションして宿泊施設・情報発信地として地域に貢献している。歴史深い尾道の町並みに溶け込む佇まいをしながら、時代とともに変容する文化が風通し良く混ざりあう新たなコミュニティスペース。サステナビリティに信を置くEQUALANDとの親和性も高い場所となった。

ー尾道LOGを選んだ理由から聞かせてください
元々尾道LOGと未来心の丘はチェックはしていたんです。今回、ディレクターの安部真理子さんからインスピレーションなどを伺っているうちに結びつきました。
ーどのような部分で繋がりましたか?
まずは色合いですね。少しアジアを感じつつ、ヨーロッパっぽい、なかなか日本の建物には無い絶妙な色合いです。
ー未来心の丘はかなり構築的なロケーションとなりました。建築的なオブジェクトとのご自身の作品性の繋がりについてどのように感じますか?
私はあまりアーティスト性やモード感のあるものは、物としては興味がなくて。写真を撮るときに女性っぽい要素が欲しいっていうのがあるんですよ。フォルムや柔らかさを感じる質感を出したかったので、ああいった場所になりました。
ー和のテイストにもこだわっていらっしゃいました
上質さを表現する時に日本のものは切り離せないから。そこをうまく伝えたかったというのと同時に、今時のテイストもちゃんと混ぜたいという思いがありました。LOGの色合いとも調和しそうだったので上手く自分がディレクションすればできるだろうと。あと、海外の方からの目線も作品作りの中では意識しています。
ー今回の撮影に置いて、最も注力した表現はなんでしたか?
上質感でしょうか。私自身、モノトーンやモノクロが好きな反面カラフルなものを使うのが苦手で。そこで派手な色合いのものをいかに質の良いものとして打ち出せるかを注意しました。モデルさんなどもそうですけれど、光とか、自然、有機物みたいなものをインスピレーションにすすめていきました。

ーナツミさんの切り撮る女性たちは、女性らしいんですがセクシー過ぎず艶っぽすぎない独特の距離感があるように思います。理想とする女性像があるのでしょうか?
作品を作るときにこうしたいというのはあまり無いですが、こうしてるのが好きっていうのは明確に持っています。女優でいうとジュリア・ロバーツ。屈託のない笑顔で、かっこいいんだけど女性らしく、自然体でいることを受け入れてるような印象。あまり作り込んでいるのは好きじゃないです。それに”かわいい”って全然興味なくて、その要素を全く入れないんですよ。もしかしたらフレンチとかもあまり入れたくないって思っちゃう。その中でも、大人っぽく見せられるのであればそれは全然良いんですけど。基本的にやっぱりモダン、ですかね。あまりエロスを感じるものは好きじゃない。ヌードとかも撮りますけど、物体として見ている感じです。
ーどういうものを見て育ってきたんですか?
私、母親と趣味がほぼ一緒で、母からの影響がすごい大きいんです。服も家具も雑貨も好きなんですけど、他人に対しての憧れが無いんです。例えば、服が好きな人たちがどんな服が好きで、デザイナーに憧れてるかという類の。それは、同業のデザイナーでも同じ。この人のここは好き、という局部的なものはあります、何が好きで何が好きでは無いかを自分で決める環境で育ってきたかなと。
ーお母さまはどのような方ですか?
センスが良い主婦ですね。仕事の相談をするのもほとんど母親だけ。母は収集癖は全くなくて、実用的。そこは、私がデザインをやる上で通ずるところがあります。母親は実用的でなければ、デザインが良くても買わない。私は、自分が使うものとコレクションをあえて切り離して考えるようにしています。その考えができると、クライアントワークがしやすい気がしているので、そういった面でブランディングは割と得意なのかもしれません。
ー仕事上の訓練はほぼしていないのも特徴的ですよね
ほんと一瞬だけ『WWD』編集部に入っていた時期がありました。学生時代は一番最初に就職したくて『Drop Tokyo』、ギャル雑誌の編集、Webのデザイン事務所など4つぐらいのインターンを掛け持ちしていました。就職してみると自分はステッカーとかちまちましたものが好きなのに、なんでここに入ったんだろうと1カ月程度で辞めてフリーになりました。いまお仕事いただけてるのは運ですね。ADになりたいっていう子はクラスにも結構いたんですが、当時はあまり興味はなかったんです。
ー手を動かすのが好きだったから?
元々音楽をやりたかったんですけど、センスがなさすぎてすぐ駄目だとわかりました。デザインとか美術の点数が良かったしパソコンも得意だし、向いてるのかなと思ってこっちに進んだんです。とにかく憧れがなさすぎて。なんなら授業もめんどくさいと思ってたし。
ーなにかを目指さずに、軸はぶれずに。好きなものは変わらずにあるから貫けるのかもしれないですね。映画が好きっておっしゃってましたよね
映画は大好きですね!アクションとかサスペンスが好き。ハリウッドはもう確実に好きです。おしゃれ映画はあんまり観ないですね。ソフィア・コッポラとか全く観ないです。覚えようとはするんですけど、全然興味が無いので出てこなくて。現実的なのとか、話の構成がある刑事ものとか、実話ベースの重ためのものも好きです。最近面白かったのは『女神の見えざる手』。銃規制法の話なのですが、社会問題の背景系も好きですね。

ーSNSによってビジュアルが先行する時代。インスピレーションも受けやすいが、模倣もしやすい環境。ナツミさんはどのように考えますか?
あんまり気にしてなかったですね。実際、みんな何かを見てデザインをしているし、デザインてパクリじゃんって思うんですよね。グラフィックがそんなに表に出ていない初期のときに手を動かしてデザインしている人たちっていうのは、本当にオリジナリティが溢れてるし、すごいなって思うんですけど。今ってパクリもなにも無いっていう感じがしてて。それはデザインだけじゃなくて、映画とかも一緒だと思っていて。だからと言って、すごく真似してますっていうのは、どうかと思います。物作りは自分が説明できなきゃいけないから。元々あるものを真似て作ってるって言えるならそれで良いだろうし。ただなにも言わずに、表面だけ似せてくるのはどうかなと。
仕事で私らしいデザインを、と求められることがあるんです。でも元々あるルールの中で、イトウさんの雰囲気をプラスしてって求められても、元々に私のチョイスが入ってないから、私らしくならないわって思うことがあるんです。クライアントワークならやるんですけど、それって私らしい要素を若干入れただけ。でもそれも、まあ良いかなっておもっています。悩んでた時期もあったんですけど、今はもう、仕方がないこととして、気にしないようになってきていますね。
ーそういう場合は”イトウナツミらしさ”を自ら選択して提案するんですか?
相手によりますね。相手が理解してくれるか、その人の世界観は私のと共通するのか。別に私のものを渡したところで、良いようにならないのであれば、切り離しちゃって良いところで動いてる人だっていうのはなんとなく思ってしまうので。

ー好きなアーティストがいるとすぐ連絡を取るようにしているとか
すぐ連絡しますね。私、一番最初の個展が、蔵前にあるカフェでやったんですけど、店主の女の子の方のセンスが好きで。話しかけたら仲良くなって、雑貨とかの趣味が合って個展をする運びになったという経緯があって。自分が良いなって思った相手もこっちを良いなって思ってくれると貴重な友達になりますし、仕事じゃなくてもすごく良い関係だなと思います。逆に話してみて、全然ちがうってなることもありますけれど。
最近知り合った少し年下の子に、歌を自分で録って配信したりをいとも簡単にしている人がいて、それを聴いたらめちゃくちゃ下手でびっくりしたんです。でもこれを平気で配信する感じとかすごく良いなって思ったりして。他にも、とある方に頼まれてポートレートを撮ったんですが、インスタグラムには私が納品した写真と若干違うものを載せていた。顔を編集したり、肌のトーンをあげたりしているのを見て、さいしょは「えっ」て思いましたし、コレができるのはブランディングが自分でできる人に限ってだとは思います。ただ、そういった変化は受け入れた方が良いなと思っています。最初は困惑したし、今後通用するのかなと危惧もしますが、勢いが強ければ受け入れられていくもの。だからあまり考えないで受け入れる方が楽しめるかなって。
ー例えば雑誌などの媒体だと、基本的にフォトグラファーに作品性を求めつつ媒体側の意図や表現手法へのコミットが前提とされています。しかし昨今、より作家性を残そうとするフォトグラファーが増えてきているという気はしています。ヴィジュアルに対するリテラシーの高さやスマホのカメラ技術の高まりとか、紙媒体の意義とか、複合的な理由があると思いますが、そこに時代性が反映されているのかも。
作品と仕事の境界線が曖昧になってきている部分もあるかもしれないですね。作家兼フォトグラファーの方がやりづらいのかなと思いますし、私は自分の作品とクライアントワークは割り切っちゃってますね。私は手が加わってもまあ別に良いやって思うけど、コントロールするのが難しいだろうなって。
要は、売れたいっていう欲が邪魔するなって思います。売れたらもちろん、できる幅も広がるし楽しいんだろうなとは思うんですけど、逆にアーティストとして活動してそれが売れたら嬉しいじゃないですか。そこの欲があるから、アーティストとして名前を出しつつ、仕事をするっていうのがあるのかなと。
私はもう自分の作品は売れなくて良いと思ってるんですよ。なんなら、大して共感してくれる人もいないだろう、程度に考えてる。もちろんいたら嬉しいけど、そもそもデザイナーとしているなら、自分がどうのよりも相手に求められていることをすることが最優先ですから。そのスタンスに関しては兄に指摘されたことで納得して自然と分けるようになりました。そうしたら楽でしたね。棲み分けしやすい。
ーナツミさんの、自分らしい作品とはなんですか?
普段通りな感じ、というか日常的な感じがすごく好きで、多分それがインスピレーションになっているんだろうなと。特別、こういうテーマだから撮りたいっていうのはなくて。伝えたい・撮りたいっていう大それたことではなく、日常の中にある良いなって思った瞬間を切りとって発信するような、自然体な感じのものを作っているときが一番自分らしいのかなと。
ー撮影のメンバーは割と固定されてますよね
自然体な感じの空気感にしていくには、やはりどうしても話のしやすいメンバーになることが多いですね。特に外国人のモデルさんには、心を通わせるように努力しています。楽しんで作ろうっていう空気を作るために、英語は喋れないですがコミュニケーションするのもADの頑張らなきゃいけないところかなと。徐々に仲間を増やしていかなきゃいけないとは思っています。

ーサステナビリティには様々な側面がありますが、無理にならない仕組みと大きく捉えられるのかなと考えています。どこかや誰かが窮屈な思いをしたり、苦しみを押し付けられたり、ということを掬いだして整備して、心地よい環境を循環させて歩みを進めていこうということだと。ナツミさんの生き方は基盤からものすごくサステナブルだなと感じています
言葉が流行化しているような部分があってそこには興味が無いんですけれど、新しいことに対して気負わないで受け入れたら良いのにとは思っていますね。例えばモデルさんでもいろんなルーツを持つ子やハーフの子も増えているのを見ると、接する機会も増えて問題が表面化しやすい部分もあるかもしれません。お互いが肩の力を抜いて受け入れて生きていける世の中になれば良いなと思いますね。
今回のビジュアルも、モデルさん達は美しいという理由だけで起用させてもらいました。モハメドくんにスカートを着用してもらったりしていますが、単純にすごく素敵だとおもうし、それが素敵だということ以上の価値観を持ち出すことがナンセンスなんじゃないかな。
ーファッション界ではジェンダーレスが当然の合言葉として成立していますが、市民とのリテラシーギャップは否めない。人種や性差について語られるときに存在する様々な課題は少しづつ更新する必要がありますよね
カタログやヴィジュアルを制作するとき、ブランドさんからモデルの肌の色を指定されることってよくあるんです。でも、コンテクストに沿っていれば私は色を問わず提案するんですよね。反論に対しては理解するけど、共感しないって伝えることもあります。
ーコレはコレ、それはそれ、と切り離して考えることが矛盾を生んできましたから。販促物を扱う場合はクリエイター側はよりメッセージを意識する必要があるのかもしれない?
でもそれも割と無理しなくて良いとも思ってます。人種の話も、身近に友人がいるとかなにかきっかけがあってから興味が広がっていく。行動を起こすことに関して無理しなくて良いと思うし、本当に変えたいなら徹底的にやったらいいとおもいます
ー最後に今後の作品のテーマ、活動についておきかせください
基本は変えないです。4月末に個展をする予定です。コロナ禍でも日常からのインスピレーションには事欠かないですし、身近なものを見る良い機会になってるかなと思って。でももしかしたら一周回って、別のところにいくかもしれないので変わるかもしれないです。

Natsumi Ito
東京を拠点に国内外で活動する日本人アーティスト。生活に溶け込むデザインや美しさを大切にし々な作品を生み出している。近年ではデザインのみに留まらず、写真、イラストレーション、ブランディングなど、肩書きに拘らないその活動は多岐にわたり注目を浴びている。
Photographer_ Riku Ikeya
Interview_ Yuka Sone Sato
Editorial Direction_ Little Lights