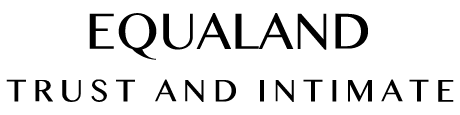ものづくりの背景に敬意を払いクリエーションを讃える。サステナブルをテーマに、アーティストや起業家をはじめ想いを共有する挑戦者たちを紹介。彼らのヴィジョンから自分らしいスタイルのヒントを見つけ出します。
視点を委ね、揺らぎを肯定する。細倉真弓が滲み出す曖昧さのある日常
写真家、細倉真弓さんの個展『Sen to Me』では古典的に切り撮られた手影に箔糸を刺繍したアナログな写真作品と、巨大なコラージュを用いたデジタル作品が展示されている。壁に掛けられた静謐な写真作品に対して空間の中央では天井からスクリーンが垂れ下がり、画面には観る者が耐えうるギリギリであろう時間を使って作品がスクリーンの中でスライドする。鑑賞者が視点を委ねられたこの展示を通して、細倉さんは人間の視点に改めて向き合う。視点というものが価値観を反映しやがて人格や社会を形成しているとするならば、それが移り変わるたびに社会や人間は変わる必要があるのかもしれない。


ー細倉さんはこれまで、女性や男性のヌード、特性の文化背景を持つ若者のルポタージュ写真やコラージュ作品など幅広く展開してこられました。今回の作品にははじめて刺繍が施されていますがその経緯を伺えますか。
ここ2~3年、写真をベースにして映像など別のメディアにスライドしていくような作り方に変わってきています。今回の初期衝動は、京都で古着屋を営んでいる友人が古着に刺繍を施したリメイクをしているのを見て、シンプルに写真に刺繍してみたいという欲望がありました。しかし工芸っぽくなるというよりは乱暴な感じで刺繍したいなと考えたんです。
ー乱暴な感じというのは、どういうことでしょうか?
写真のプリントって常に丁寧に扱われがちで、それがちょっと面倒くさいんですよね。そこで、あえて穴を開けたりダメージを与えるのが面白いんじゃないかと。本来、邪魔者とされている存在をあえて取り入れたいと思ったんです。

ー仄明るく写っている手の印象が強いですがこれはどのように撮影したんですか。
フォトグラムといって、暗室で写真の印画紙に直接手を置くことで影が白く残るという手法で、「カメラを使わない写真」と呼ばれています。ここしばらくデジタルの作品作りをしていたのですが、コロナ渦の中で形になるものを残したいという欲望が湧いてきたんです。暗室で現像液や定着液に漬けて浮かび上がってくるアナログな写真に実物観や実在感を求めたことと同じように、刺繍作品も現実空間でイメージを付け加えたいという思いがありました。

ーコラージュ作品は、画面上でゆっくりと動き、巻物のような感覚を与えるデジタル作品が展示されています。コラージュが移動することで物体が別のものに遷移していき、一連のストーリー性を感じさせるものとなっていました。スクリーンごとにシンクロナイズしているようで、さまざまな想像を掻き立てられます。
刺繍もデジタル作品も一貫して「視線の動き」を捉えています。2019年に作品『NEW SKIN』でもコラージュ作品をスクリーンで映し出す作品を展示したのですが、そのときはもっと乱暴に見ている人の視点を無理やりわたしの視点に合わせていました。対して今回は、見ている人の視点が勝手に画面のなかを動くように展示しています。この映像の作品は横長につくられていて、全部見るには15分かかるんです。2秒で見られる写真を15秒かけてみることは全く別の体験になります。長さの違うコラージュが連想ゲームのように配置されているので、見る人それぞれが勝手に物語を見ちゃうっていう面白さがある。
ーコラージュに消費的な物体が使われているのが印象的でしたが、どのような意図があったのでしょうか?
普段の生活空間にありふれた物って、写真としてじっくり見ると全く違うものに感じたりする。なんてことない瞬間が、写真にするとどうにも不思議なものに見えてしまう、という不思議さや面白さが気になっていて。日常的なものや路上にあったりする当たり前のものをもう一度よく見てみると、実は現実ってよく出来てるなぁと感じます。



ー2019年の『NEW SKIN』から派生し、今年5月の『ジギタリス、あるいは一人称のカメラ』展、そして今作のコラージュ。これら昨今の作品群は自他の視点というものに焦点を当てた流れとなっています。『NEW SKIN』でゲイ雑誌のコラージュを使用したのはどのような意味があったのでしょうか。
“男性の身体をどうみるか”を大枠のモチーフとしていたのですが、それを私以外の視点を入れて形成したかったんです。自分が写真を勉強していて、途中でヌードを撮るようになったんですけれど、男性のヌードって写真史でも女性に比べてすごく少ないんです。女性を性的対象として美しく撮られている作品は多いんですが、特に女性が主体で男性のヌードを撮っているのが本当に少ない。そこで男性の身体をどのように撮ると魅力的に見えるのかを学んだのが、同性愛男性の映画監督や写真家だった。本当は女性がそれをしても良かったはずだったけれど、それをする場所がなかった。男性の体を魅力的に撮っている形を見せてくれたゲイ雑誌が自分の写真の原点みたいなところにあるので、そのオマージュっていうのがあったんですよね。


ー細倉さんの作品では「境界線」がもう一つのキーワードとしてあります。社会の様々な部分で細倉さんは作品を通してどのように境界線と対峙しているんでしょうか。
『NEW SKIN』を作っている頃に、ダナ・ハラウェイの著作にすごいハマっていたんです。人間の概念みたいものがだんだん曖昧になっているとか、機械によって人間の境界線がどんど拡張していると。今スマホで何でも検索しますけれど、それはある意味、脳がスマホまで拡張していると言えるじゃないですか。自分があたりまえだと思っていた境界線が知らず知らずのうちに広がってたりするんだろうなと。
境界線が浸蝕されると体感的に怖かったり、それをすごく嫌う人もいる。人種問題にしてもそうなんですが、全てが一緒になると自分が信じていたものが曖昧になってしまって、自分がよくわからなくなることが怖いから反対するといった心理が人間にはあるのかなと。ジェンダーやセクシャリティもそうで、自分がこういうもんだと思っていたものが揺さぶられると、自分が不安になるから喧嘩になったりする。でもそこを揺さぶられてもいいんだよ、っていうか、もともと曖昧なものだから自分を型にはめなくてもいいというか。そういう曖昧な状態を肯定するものとして自分が撮ってるものがあるといいなと思います。


ー境界線という曖昧さの存在を意識するようになったきっかけは何でしたか?
扱ってる被写体にヌードが多かったことですね。自分の“異性愛者”というセクシャリティを自覚することが多かったと同時に色々なセクシュアリティの人たちを撮る中で自分が揺らぐのを自覚する瞬間みたいなのがあって、実はそれって曖昧なものなんじゃないかなと思ったり、セクシャリティに限らず、人との向き合い方や政治の考え方にしても、思い込みが簡単に揺らぐ可能性があるんじゃないかと。だから、そこに対する拒絶はあまりしたくないというか。自分が変わる可能性を受け入れられる状態になるといいなっていうのはありますよね。人は変わる、ってことですよね。確固とした自分って実はあんまりなくて、常に変わっていく。自分が認識していた境界線自体も、時代や自分の経験で遷移する流動的なものではないだろうかと。


ー御祖母様が芸姑をされていたそうですが、それが女性の自立や現代のフェミニズムをはじめとした細倉さんの考えに対する影響を感じますか?
私の時代は芸妓はもう引退していて、実際の現場は見ていないんですけれど。女性がサヴァイブするために、そういう生き方があったっていうのは結構親近感があります。女性が働いて生きて行く、自分で自分を生きのびさせるために仕事=芸妓をするという生き方です。私は小さい頃から何かを作る仕事をしたいと思っていて、それを親に反対されることもなく今はそれをできているのですが、現代女性にとって選択肢が増えたのは先人のおかげですよね、祖母の時代だと生き方を選べなかったわけですし。未だいろいろと問題はありますが、やりたいと思ったことを性別を理由に我慢させられず、個人の資質で選べるように、選択の自由は無限に増えてほしいと思います。
細倉真弓
写真家。東京/京都在住。触覚的な視覚を軸に、身体や性、人と人工物、有機物と無機物など、移り変わっていく境界線を写真と映像で扱う。立命館大学文学部、及び日本大学芸術学部写真学科卒業。主な個展に「NEW SKIN |あたらしい肌」(2019年、mumei、東京)、「Jubilee」(2017年、nomad nomad、香港)、「Cyalium」(2016年、G/P gallery、東京)、「クリスタル ラブ スターライト」(2014年、G/P gallery、東京)、「Transparency is the new mystery」(2012年、関渡美術館2F展示室、台北)など。
Instagram @mayumi_hosokura
http://hosokuramayumi.com/
『Sen to Me|細倉真弓』展
会期:9月4日(土)~10月23日(土)
開廊:火~土 11:00 – 18:00
休廊:日曜・月曜・祝日
会場:Takuro Someya Contemporary Art
〒140-0002 東京都品川区東品川1-33-10 TERRADA Art Complex 3F TSCA
Interview_ Yuka Sone Sato
Editorial Direction_ Little Lights