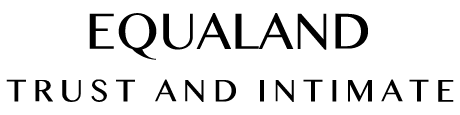物を買う、発言する。そんな私たちの小さなアクションが社会を動かしていきます。まずは、身の回りや世界にはびこる社会問題に目を向け意識を変えることから。様々な執筆家を迎え、それぞれの気づきから考えを促します。
「なにを着てもダサく見えていた私がフェミニズムを知って変わったこと」フェミニスト笛美
21年7月に上梓した『ぜんぶ運命だったんかい』では、一冊を通して、筆者の笛美さんのフェミニズムの出会いをきっかけにした、社会の歪んだ“当たり前”への気付きが赤裸々に描かれている。フランクな口調で吐露された実体験からは、自分が自分らしくいられるメンタルづくりを応援する笛美さんからの優しくも強いメッセージが心に響く。フェミニズム視点によって見えないものが見えたとき、それは生きやすさへの大きな躍進になる。長く愛せる服を選ぶという題目から、あなたはあなたの日常に溢れるどんなイシューに気づくのだろうか。
自分だけダサく見える現象
「なんで自分は何を着てもダサく見えるのか?」これは人生最大のミステリーだった。小学校の時はみんなひとしく近所のスーパーで売っている服を着ていたはずなのに、なぜか他の子は立派に見えて、自分だけみすぼらしく見えた。中学、高校に進んで服の出所がパルコやsuzutanになっても自分だけダサく見える現象は変わらなかった。大学入学時には、百貨店で買った流行りのトレンチコートを着て行った。みんな似たようなトレンチコートを着ていて、いわゆる量産型大学生っぽかったにもかかわらず、なぜか自分だけダサく見えた。
お金があればおしゃれになれる?
社会人になってお金を得た私は、その多くをファッションに注ぎ込んだ。お金の力にものを言わせて「自分だけダサく見える現象」から解放されたいと思ったのだ。映画や本を鑑賞するほどの心の余裕もない私にとって、百貨店やファッションビルでする洋服のお買い物だけが娯楽だった。忙しすぎて友達はどんどん減っていくけど、自分のお金で買った服はどんどん増えていった。
モテ系の服から個性派の服までさまざまなテイストの服を買い漁った。職場の人や好きだった人の反応をあれこれ想像しながら、「これじゃ引かれるかな?」「調子に乗ってると思われるかな?」などと思いながら服を選んでいた。忙しすぎて洗濯もできなかったので、服を洗うよりも新しく買うことで着る服をまかなっていた。おしゃれなカットソーやワンピースを買った後でタグを見たらドライクリーニングオンリーだったりして、ますます洗濯できないことに拍車がかかった。高いのに手入れのされていない服をきている自分は女としてだらしなく失格だと思った。
当時、似合わない服は売ったり捨てたりしていたけど、別にすぐに捨てる服を買おうなんて思ってたわけじゃない。いつだって一生ものの服を買おうと思ってはいた。おしゃれな知人にショッピングに同行してもらい、一時的にセンスが上がったかのように思えた時期もあったが、それでもなぜか自分だけダサく見える現象は治らなかった。
なぜみんなはこんなにおしゃれなんだろう?どこでファッションを学んできたの?衣装ボックスからあふれ出たクシャクシャの服たちをゴミ袋に入れるときは、自分の心もクシャクシャに潰されるような気持ちだった。
ファッションには女の子への夢と抑圧が詰まってる?
30代前半に海外に滞在していた時にフェミニズムの存在を知った。その国では男女格差が小さく、女性がノーメイクで、服装もよほどのイベントでもない限りジーンズにスニーカーとラフだったけど何も言われていなかった。日本に帰ってくると、日本の女の人はみんな頭の先から爪先までスキがなく完ぺきできちんとしたファッションをしていた。公共交通機関で歩きにくいハイヒールを履いてる人も多い。コーディネートという小さな世界に日本の女性に求められている「完ぺき」が凝縮されてるように見えた。もしかしたらファッションには社会が女性に求める夢や抑圧のようなものも詰まっているのかもしれないと思った。きっと自分がいま着ている服にもその抑圧が入っているんだろう。これから私はなんのために服を着て行こうかと気になり始めた。
フェミニストはどんな服を着てもいい
フェミニストになったからと言って、服の好みがすぐに変わるわけではない。生身のフェミニストの人に接するようになって気付いたのだが、フェミニストにはフェミニンな服の人もいれば、ボーイッシュな服の人、奇抜な服の人もいれば、地味な服の人もいて、それについて誰も突っ込まない。「そんなにピチピチした服を着て、よほど自分のスタイルに自信があるのね」とか「ミニスカートを履いていたなら痴漢されても文句はいうな」などと言う人はフェミニストにはいなかった。フェミニストはそういった発言をしないし、むしろそれに対して怒ってくれるのだ。そしてどんな服を着たって、どんな体型でいたって、ヘアメイクをしていたって、文句を言わないでくれる。それが少なくとも私が見たフェミニズムの世界だった。これまでもファッション誌で「自分らしく」というコピーが散々書いてあったのに、フェミニズムを知って初めて「自分らしく」生きていてもいいんだと思えたのだ。
ファッションとの和解はできたのか
「なんで自分は何を着てもダサく見えるのか?」その思いはフェミニストになった今でも消えることがない。むしろそれに立ち向かうために私はフェミニズムを使っているのかもしれない。 だけどフェミニズムのおかげか加齢のおかげか、ファッションというものへの激しい劣等感はだいぶ落ち着いてきたように思う。特に今年の秋冬は、元から持っていた服と新しく買い足した服を織り交ぜながら、自分とファッションとの関係がかなりうまくいっているような気がする。たくさん服を買って、たくさん捨てていた頃の自分は苦しかった。自分で買った服が長く着れると、自己肯定感が上がることにも気づいた。だから今はできるだけ長く愛せる服にだけお金を使うようにしようと心がけている。
長く愛せる服を選ぶために
長く愛せる服を選ぶには、自分に「やせ我慢」をさせないことだ。いまの自分にとってやせ我慢をしないというのは、何よりまず水洗いで洗濯ができること。価格は安いけどお手入れに手間がかかるファストファッションより、お手入れが少なくてもバシッと決まってくれる服を多少高くても買うこと。ボトムスならウェストゴムなこと。スタイルがよくなったら似合う服じゃなくて、いまこの瞬間に着こなせる服を買うこと。違和感が少しでもあったらたとえ安くても買わないこと。古着でも新品でも必ず納得のいくまで試着をすること。愛すべきデザインの服は出し惜しみせず頻繁に着ること。ワードローブはちょっと物足りないくらいでもいっぺん我慢してみること。これはあくまでもファッションに自信のない私の場合で、他の人には当てはまらないかもしれないが、そんな工夫をしながらファッションとの関係をどうにか改善しようと試みている。
これまでファッションでたくさんの失敗を繰り返して、自分にも環境にもやさしくないことをたくさんしてきた。だけどフェミニズムを知ったことで、私は完璧にできないなりに、できた自分を認めてあげられるようになってきた気がする。今シーズンこそ、そして次のシーズンもずっと、愛せる服を末長く運用しつづけたいと願っている。
笛美/フェミニスト
トレードマークは青い顔の女性。フェミニストという価値観や視点を通してマイノリティに対するバリューの見直しと改善を提案したり、SNSメディアで意見発信をしている。絵日記を綴るインスタグラムでは日常的に感じる歪みや社会問題を描く。Twitterデモ「#検察庁法改正に抗議します」の仕掛人。『ぜんぶ運命だったんかい』は亜紀書房より発売中
Instagram @fuemiad
twitter @fuemiad
Artwork_ Maddalena R
Editorial Direction_ Little Lights